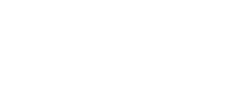- Home
- 李参平の歴史
李参平(初代金ヶ江三兵衛) 〜朝鮮人陶工から始まった有田焼
16世紀末「壬辰(じんしん)・丁酉(ていゆう)倭乱(文録・慶長の朝鮮出兵)」は日本陶磁史にとって、大きな発展のきっかけとなりました。それまでの日本では六古窯に代表される瀬戸・常滑・越前・信楽・丹波・備前などの陶器の製造はあっても磁器の製造はありませんでした。
17世紀以降、西日本を中心に定着した朝鮮人陶工といえば、薩摩焼の沈当吉・上野焼の上野尊楷・高取焼の高取八山・萩焼の李敬そして有田焼の李参平などが挙げられます。
金ヶ江家文書によると、鍋島藩初代藩主鍋島直茂公によって佐賀の地に連れてこられた李参平は初め鍋島藩の老中、多久家に預けられます。その領内で今までの技術を活かし築窯しましたが、思い通りの焼物が出来ませんでした。やがて、白磁に適した陶土を探すため鍋島藩内を歩きまわります。そして、1616年に李参平が有田の泉山にて良質の磁器鉱を発見したと書かれています。

初代李参平像

泉山磁石場
しかし、近年の研究では1610年代初頭に有田の泉山に良質の磁石鉱を発見したとされています。その後、李参平は有田の上白川・天狗谷窯に窯を築き現在に近い窯業のシステムを確立させていきます。1616年には鍋島直茂公に「磁器」を献上したことにより、有田焼の創業とされています。
これらの功績を称えられ多久家が李参平の出身地、錦江島の在所から名をとり「金ヶ江三兵衛(かながえさんべえ)」と名のらせました。
その後「有田焼」は鍋島藩を支える産業の一つとなり、VOC(東インド会社)をとおして世界へ輸出され、その名を知られるようになります。
そして、有田の行末を見守りながら1655年8月11日李参平は亡くなります。有田町内にある龍泉寺の過去帳に戒名が刻まれ、天狗谷古窯の近くに墓碑も創建されました。このことは当時の日本ではとても稀な事で、最上級の手厚い庇護を受けていたことがわかります。

創建された初代李参平の墓碑
李参平が亡くなった直後でもある1656年頃「八幡社」(現在の陶山神社)が創建されました。主祭神は応神天皇であり、後に鍋島藩祖鍋島直茂と陶祖李参平をあわせて祀るようになりました。今でも有田皿山の人々の信仰を集め、参拝する人々は絶えません。
有田焼創業から300年を経た1916年。有田の先人たちは「陶祖 李参平碑」の建立を決めます。当時の時代的背景を考えると画期的な計画であり、感謝と報恩を象徴する碑として工事が進められました。
2年後の1918年町内を一望できる陶山神社の後背に、有田を見守るかのように碑が完成します。
この碑の前で毎年5月4日に「陶祖祭」が行なわれ、現在、韓日両国の関係者が参列して開催されています。

陶山神社 磁器鳥居

有田李参平顕彰碑 陶祖祭
李参平を初代とする 金ヶ江家系図
-
初 代 三兵衛(初代 李参平)
朝鮮忠清南道金江人帰化
明暦元年(1655年)8月11日卒 戒名「月窓浄心居士」 -
二 代 三兵衛(始 与助左衛門)
宝永元年(1751年)1月26日卒
-
三 代 三兵衛(始 惣太夫)
享保9年(1724年)2月卒
-
四 代 三兵衛
明和元年(1764年)10月卒
-
五 代 三兵衛(始 惣太夫)
明和6年(1769年)12月19日卒
-
六 代 惣太夫
文化3年(1806年)10月卒
-
七 代 三兵衛
天保6年(1835年)7月19日卒
-
八 代 惣太夫
万延元年(1860年)4月21日卒
-
九 代 三兵衛
安政3年(1856年)12月21日卒
-
十 代 義三郎
明治17年(1884年)5月21日卒
-
十一代 米助
明治42年(1909年)10月2日卒
-
十二代 義平
昭和25年(1950年)12月7日卒
-
十三代 義人
大正9年(1920)3月3日生
平成29年(2017)2月20日卒 戒名「本願義興居士」 -
十四代 省平
昭和36年(1961)1月9日生